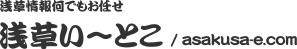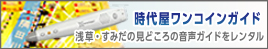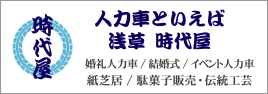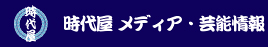|
|
浅草というとやはり「浅草寺」中心の繁華街を想定しますよね。 でも、繁華街浅草だけじゃ、終わらないのが浅草なんです。
皆様の感想・ご意見・想い出話、皆様がお持ちの古い写真などどしどしお寄せ下さい。
|
|
「江戸東京学事典」によると…
「台東区東側約半分の地域に対する総称地名で、隅田川西岸一帯を浅草とよんだ。範囲は東が隅田川、南が神田川、北が思川別名駒洗川で囲まれる地域。 明治11年(1878)~昭和22年(1947)まで台東区発足まで区名にもなった。 浅草の地名の由来には、諸説があり、アイヌ語のアツアクサ(海を越すという意味)にちなむとか、チベット語のアーシャ・クシャ(聖のおわす所の意味)に由来するなど。 定説は「江戸往古図説」が「往古下谷より此わたりへかけて平地にして武蔵野の末にて草もおのづから浅々しき故浅草と云しなるべしといへりさもあらんか」と述べているのをとる。 |

|
| 鎌倉時代、源頼朝が鶴岡八幡宮を造営したときに、いい大工がいないので浅草から宮大工を呼び寄せて従事させた。 宮大工の鎌倉派遣に先立ち、渡船を増やし人の往来が激しくなった。 室町時代末期になると、浅草寺境内にて、市(物品交易の場)が開かれるようになった。 |
| 江戸時代、江戸は著しい発展を遂げ、浅草も吸収される。 |
| 大正18年(1590)、徳川家康は江戸に入ると、浅草寺を祈願寺と定め500石を寄進した。寛永13年(1636)、三代将軍家光は四月焼亡の本堂を再建した。だが、6年後にまた焼けてしまう。家光は再度、浅草寺の復興を行ない、1648~1649にかけて、本堂・五重塔・仁王門・雷門を建立した。 江戸時代の初期に浅草寺境内に茶菓を提供する水茶屋が現れた。江戸時代の茶屋は休憩所のことで、茶店がその創始だという。 次に大道芸。浅草寺の2ヵ所で興行されていた。表参道(現仲見世のある通り)、仁王門をくぐろうとする直前の右手。 |
|
明治時代に入り、明治6年(1873)1月15日東京府知事 大久保一翁は、5ヵ所の公園を決め、太政官に申告した。 ・上野寛永寺 ・浅草寺 ・芝増上寺 ・深川富岡八幡 ・飛鳥山 浅草寺境内は「浅草公園」として命名された。 明治17年(1884)1月、6区に分けられ、同年9月には7区を新設した。 1区…浅草寺本堂周囲。浅草神社、二天門、仁王門、五重塔、淡島堂 2区…仲見世 3区…浅草寺本坊伝法院の敷地 4区…公園中の林泉地。大池、ひょうたん池のあった付近。 5区…奥山と呼ばれたところで公園の北部。花屋敷はこの5区内。 6区…見世物の中心地。旧ひょうたん池跡をのぞく現在の映画街。 7区…公園の東南部。浅草馬道町1~5丁目 |
| その後、6区は東京人士に親しまれ、人が群集した。 |
| 明治16年(1883)、浅草寺境内奥山西側の田圃を掘って池を造り、掘り出した土で、南側と西側の池畔を築地し、街区を造成。池は俗に「ひょうたん池」と呼ばれる。 明治20年(1887)、人造の富士山が出現。らせん状の登山路を登り、頂上で展望を楽しんだという。人気がイマイチで明治23年には取り壊され、日本パノラマ館が開館。絵を360度展望できるようにした見世物。同じ年に凌雲閣が開業。「浅草12階」と呼ばれて人気を集めた。関東大震災で崩壊するまで浅草のシンボルでした。 |

|
|
浅草六区の興行街には劇場、映画館、寄席などが20軒近くも軒を並べ、 休日には兵隊や、そのころ「丁稚(でっち)」と呼ばれた若い労働者、学生などでにぎわった。 映画の入場料が一流封切館で20銭のころ、割引が常識の浅草では7銭がふつう。 丁稚でも浅草では1日遊べたんです。 明治36年(1903)わが国初の活動写真常設館として、電気館が開館。 大正のオペラ、昭和初年のレビュー・軽喜劇、 昭和40年代にかけて、第一線で活躍した芸能人の大多数は浅草育ち。 その後、浅草の名物劇場などは少しずつ姿を消して形を変えていった。 |

|

|

|

|
Photo出典:台東区図書館蔵・新撰東京名所図会(明治40年ごろ刊行)・東京名所画帖(明治末頃刊行)・大東京写真帖(昭和5年刊行)