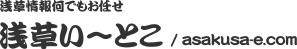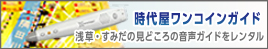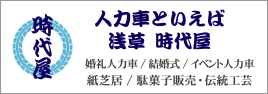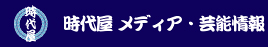待ってました!
あの 平成中村座が浅草・隅田公園に帰ってきます!
今回は、平成23年11月~平成24年5月までの
歌舞伎ロングラン公演です。
楽しみですね~!!
※情報は随時更新していきます。

 |
平成中村座 五月大歌舞伎 >>詳しくはこちら |
 |
平成中村座 四月大歌舞伎 >>詳しくはこちら |
 |
平成中村座 三月大歌舞伎 >>詳しくはこちら |
 |
平成中村座 壽初春大歌舞伎 >>詳しくはこちら |
 |
平成中村座 十二月大歌舞伎 >>詳しくはこちら |
 |
平成中村座 十一月大歌舞伎 >>詳しくはこちら |
 |
浅草い~とこ「歌舞伎鑑賞入門」 >>詳しくはこちら |



「歌舞伎」の語源は、その演出形式の中にある音楽的要素を「歌」、舞踊的要素を「舞」、科白劇(せりふげき)的要素を「伎」で表わしているが、実は比較的新しく作られた当て字。古くは「かぶき」と仮名で書き、流行の先端をゆく、もの珍しいことをするという意味の動詞「傾く」(かぶく)が名詞化したものだといいます。
慶長八年が歌舞伎元年(1603)と言われています。
出雲の阿国がその創始のスターだったとか…
京都五条あるいは三条や北野神社で興行したのが爆発的な大当たりとなる。絹の黒い僧衣をつけ、首から真紅の紐で胸に吊った鐘を叩きながら念仏踊りを踊ったり、男装して胸に十字架をつけた阿国の興行は評判に評判を呼んでいたといいます。
阿国の人気にあやかって、登場した歌舞伎。
しかも女歌舞伎だったというからビックリします。
だが、寛永六年(1629)、風紀上のトラブルが続いたことより、女歌舞伎が禁止される。
そこで現れたのが、若衆歌舞伎。若衆が女の役を演じることになった。
三代将軍徳川家光は、若衆好みだったといいます。
しかし、承応元年(1652)に若衆歌舞伎も禁止されてしまう。
そして次に現れたのが、野郎歌舞伎の時代です。
若衆の前髪を剃り落として、野郎あたまだけになった役者(男)だけで、芝居が演じられる。男優が女優にかわって女の役を演じる女形の登場がこのころです。
元禄時代は、歌舞伎の第一の発展期です。
上方(京、大阪)と江戸では、違った特色が強く打ち出されたりした。
初代市川団十郎が江戸の開祖である。
元禄時代は、五代将軍綱吉の冶政下にあった。世の中に活気があふれ、文化芸術は盛んになった。
享保時代には、歌舞伎には2つの大きな特色を加える。
1つが、人形浄瑠璃のヒット作の歌舞伎への移入、もう1つは、多彩な音楽の導入。
三味線が広く普及するようになった。
この頃、江戸四座(櫓をあげることが許された官許の劇場)は、この時以来、中村座、市村座、森田座、山村座でしたが、山村座は遊興が乱脈と指弾され、永久お取り潰しを命じられる。
歌舞伎の発達とともに舞台も進化していき、廻り舞台などの仕掛けや工夫もとりいれられました。
また、その後、2大スターが登場する。
鶴屋南北、河竹黙阿弥である。河竹黙阿弥は江戸歌舞伎を、明治時代までかかって集大成したといっていい。そして時は経ち、江戸期の現代劇が、古典となった。
天保一二年(1841)の中村座と市村座の焼失から、森田座を加えた江戸三座は浅草へ移転を命じられる。森田座の「森」という文字がいけないと、安政五年(1858)に「守」に改める。明治元年、新富町に劇場を移転して、座名も新富座とする。
二十二年に歌舞伎座が開場するまで、ここが東京の第一級劇場でした。
明治中期から歌舞伎の脚本を座付狂言者でなく外部の劇作家が提供するケースも増え、「新歌舞伎」などが生まれた。別に「スーパー歌舞伎」なども生まれた。
歌舞伎は日本を代表する古典演劇としての声価はますます高まっている。

役柄 |
●女方(おんなかた)
|
●立役(たちやく)
|
隈取(くまとり) |
歌舞伎の最も印象的な化粧。隈は描くとはいわず「隈を取る」と表現する。隈を取るのは、超人的な力の正義の味方、邪悪な心を持つ大悪人、鬼畜や神仏の化身、道外役など。役の性格がひと目で分かるような役割も果たしている。 「紅隈」は正義、血気盛んな若さ、「藍隈」は陰険で冷血、「代赭隈」(茶色)は神仏や鬼畜の化身を表している。 |
かつら |
役者の演じる人物の身分や職業、年齢、境遇を衣装とともに視覚的に印象づける重要な役割。 |
幕 |
歌舞伎の幕は原則として「引幕」を用います。「引幕」は江戸時代、幕府に許可された劇場にのみ使われた幕だったため、公認されていない神社の境内などで興行した芝居では使うことができず、いわゆる緞帳で舞台と客席とを仕切っていた。明治に入り、どの劇場も緞帳を使うようになった。「引幕」には定式幕と役者へ贈る贈り幕がある。ほかに道具幕、浅葱幕、夜の場面に使う黒幕、消し幕、花道や上手、下手の出入りに使う揚幕がある。 |
廻り舞台
|
大道具 |
歌舞伎の舞台構造が整ってくると一定の様式を備えた舞台が作られるようになってきた。 また、大仕掛けといって観客の目前で廻り舞台やセリを使わずに舞台装置を転換させることもある。 |
道具を使った仕掛けには、観客を楽しませるものがたくさんある。衣装にも仕掛けがあり、一瞬のうちに衣裳を替えることで正体を現す演出にも使う。 |
歌舞伎はさまざまな芸能の影響を受けて成り立っているが、中でも人形浄瑠璃(文楽)からの影響が深い。歌舞伎の義太夫を「竹本」ともいう。歌舞伎の演目の音楽には「長唄」があり、語りの要素の強い音楽には「常磐津」や、繊細で技巧的な節廻しの「清元」がある。 |
ツケ |
立廻りや人物の出入りの際の小気味よい音をツケと呼ぶ。ツケは動作に音をつけるという意味で、様式的な演技・演出に不可欠です。舞台上手の幕だまりの近くで、拍子木のような形をしたもので「ツケ板」を打つ人を「ツケ打ち」という。
|
分類 |
時代物 |
無断転載をお断りします!